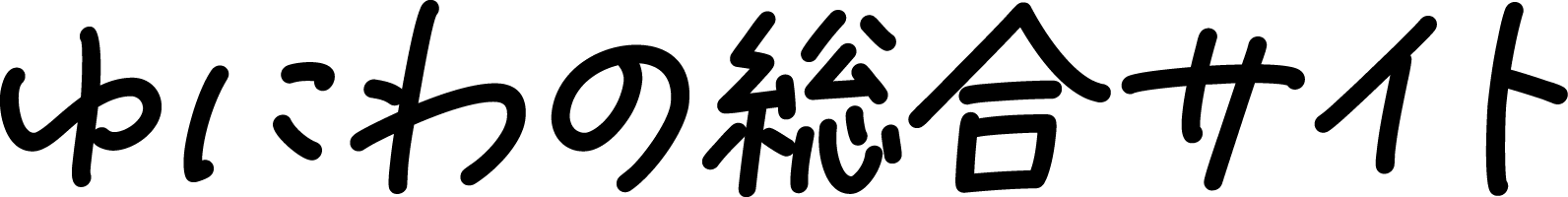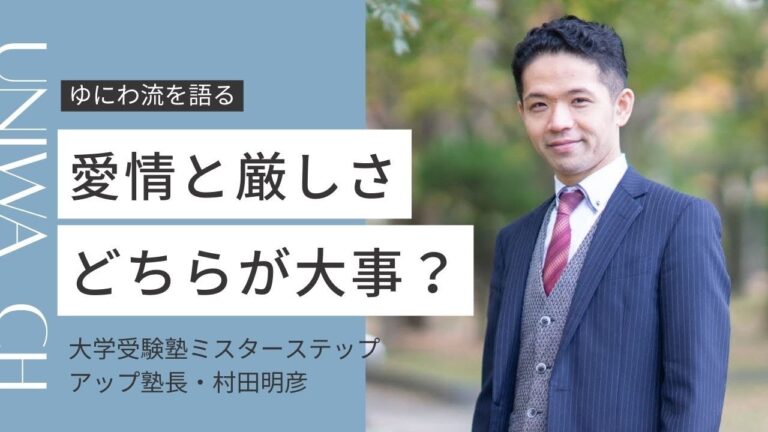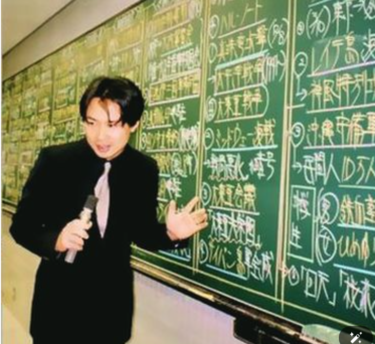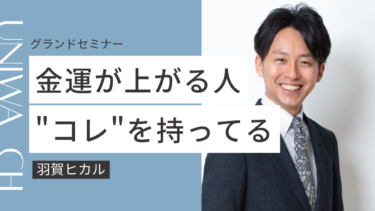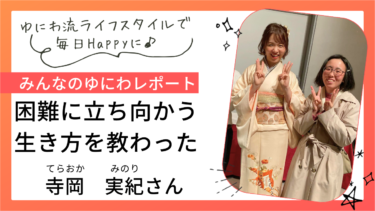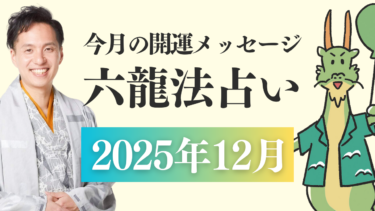子育て中の夫婦関係、どうしていますか?
子育て中のご夫婦の関係は、どのように築いていらっしゃるでしょうか。
一般的には、主に奥さまが子育てを担っていらっしゃるご家庭が多いかもしれませんね。奥さまとお父さまの関係性、そしてお子さまとの関わり方は、ご家庭によって本当にさまざまです。
たとえば、「あなたは全然、育児を手伝ってくれない」と感じるお母さまもいらっしゃいますし、「わたしがこれだけ育児を頑張っているのだから、せめてこれくらいは協力してほしい」と願うご夫婦もいらっしゃるでしょう。
そうした、ご夫婦それぞれの関係性の中での「バランス」があるのですね。
子育ての鍵は「母性」と「父性」のバランス
じつは、この「母性」と「父性」のバランスが、子育てにおいて非常に大切だと、わたしは以前から北極老人から教わってきました。
母性とは、子どもを受け止め、安心感を与え、そして常に面倒を見ていく役割を指します。いわば、子どもの心の拠り所となる存在ですね。
一方、父性とは、子どもが進むべき方向性を示す役割です。人生の羅針盤のようなイメージでしょうか。
このバランスが崩れ、たとえば母性に偏りすぎると、どうしても「子ども中心」の考え方になってしまいがちです。
父性の威厳、揺らぐ? 娘からの鋭いメッセージ
わが家の場合も、わたしは普段、仕事に出ていますから、子どもと過ごす時間の絶対量でいえば、どうしてもお母さんの方が圧倒的に多くなります。
そのため、自然と母性の方に傾きやすくなる傾向があるのですね。
そうなると、家庭の中に偏りが生じてしまい、「子ども、子ども、子ども」という状態になりかねません。そして、そのような状況では、子どもがお父さんに対して少し冷たい態度をとってしまうこともあるのです。
じつは、わたし自身も、娘に冷たくされた瞬間がありました。まだ娘が1歳半にもならない、本当に小さい頃のことですが……。
妻が一生懸命、子育てにエネルギーを注いでいる中で、わたしが仕事から家に帰り、「ああ、疲れたな」と、少し気を抜いていた時のことです。
すると、1歳半の娘が、とことことわたしのそばに近づいてきました。そして、とても可愛らしい表情で、じっとわたしの顔を見つめるのです。
「何か言ってくれるのかな?」と思いました。特に子どもに癒やしを求めているわけではありませんでしたが、あまりにも真剣に見つめてくるので、「何か話したいのかな、それとも甘えたいのかな」と、心待ちにしていたのです。
ところが、次の瞬間、娘はとても険しい表情になり、はっきりとした口調でこう言いました。
「タンサン!!」
「え、炭酸?」と思わず聞き返しました。
わが家では炭酸水を作ることができ、娘はこのシュワシュワした飲み物が大好きなのです。
普段、よその場所では「タンサン、ください」と、とても可愛らしくお願いするのですが、その時のわたしに対しては、まるで命令するかのように、険しい顔で「タンサン!!」の一言。まるで「早く炭酸を作れ!」と言わんばかりの態度でした。
危機感から生まれた対話と、新たな家族の形
「これは、まずいぞ」と、その時わたしは強く感じました。
わたしは普段から、「現代社会におけるお父さんの位置づけは、家庭内で軽視されがちだ」という話をしています。たとえば、家庭内の序列が「お母さん、子ども、ペット、そして最後にお父さん」といった具合になってしまう、というような。ドラマなどでも、お父さんが尊敬されず、父性の威厳が失われていく様子が描かれることがありますよね。
そのような状況は、家庭の崩壊につながりかねません。子どもも母親も進むべき道を見失い、お父さんは子育てから目を背け、仕事に逃げてしまう…という構図は、決して珍しくないのかもしれません。
わが家も、まさにその一歩手前だったのかもしれない、とその時感じたのです。
このままではいけない。
そう思い、すぐに夫婦でしっかりと話し合うことにしました。子どもの表情や態度は、親に対する大切なメッセージだと捉えているからです。
そして、以前から考えていたように、子どもは親だけでなく、第三者の手も借りて育てていくことが大切だと再確認しました。娘が2歳になるタイミングで、保育所に預けることを決めたのです。
それまでは、まだ子どもが幼かったため、どうしてもお母さんと一緒にいる時間を長く取っていました。しかし、早い段階から保育所を利用することで、夫婦で話し合う時間を確保し、仕事や家庭のことについて、二人で共に考えていく時間を大切にするようにしました。
家族全体のことを考え、そして何よりも夫婦の関係性を中心に据えて、家庭のあり方を見直していこう。そう決めて、少しずつシフトしていったのです。
「安心」と「方向性」が調和した、理想の学び舎
わたしがかつて入塾していた「ミスターステップアップ」という塾の環境も、まさにこの「母性」と「父性」のバランスが絶妙でした。塾を運営されていた北極老人とその奥さま、お二人が作り出す空気感が、それを体現していたのです。
奥さまは、いつもわたしたちのためにおにぎりを作ってくださったり、温かい紅茶を入れてくださったり、塾の細々としたことをすべて引き受けてくださいました。
そのおかげで、わたしたちは塾にいるだけで、深い安心感を得ることができたのです。わたしたちはそれを「安心の気」と呼んでいましたが、塾には常にその穏やかで温かい「気」が流れていました。
そして、「父性」という意味では、北極老人が常にわたしたちに人生の指針を示してくださいました。「人生とは、本来こうあるべきだ」「20代、30代という時間は、このように生きるべきだ。
だからこそ、10代後半の今、真剣に勉強する必要があるのだ」と。その力強い言葉によって、わたしたちは進むべき方向性を見出し、育てられてきたのです。卒業生であるむすび大学ナビゲーターの川嶋さんや、神社チャンネルの羽賀さん、わたしは、受験生時代を通して、そのように導かれてきたと実感しています。
安心感が、子どもの力を引き出す
その塾には、父性としての厳しさや威厳と、母性としての温かさや受容、そして「常にここにいていいんだ」と感じさせてくれる安心感が、見事なバランスで存在していました。だからこそ、塾全体の空気が、一方的な価値観の押し付けではなく、すべてを受け止めてくれる、まるで心のオアシスのような場所になっていたのだと思います。
そのような安心できる場所だからこそ、子どもたちは落ち着いて勉強に集中できる。そう言われています。
本当に安心できる空気が流れている場所では、その「気」が自然と子どもたちの集中力を高めていくのです。
家庭を超えて。組織にも活きる「母性」と「父性」の視点
これは、今回お話しした家庭という場に限ったことではありません。たとえば、地域コミュニティや、ご自身が所属されている会社などの組織においても、同じことが言えるのではないでしょうか。
どれだけ「安心できる空気」がその場に流れているかということは、仕事のパフォーマンスや集中力にも、きっと大きく関わってくるはずです。
ですから、常に「方向性を示す人」と「受け止める人」、その両方の役割が存在し、そのバランスが取れていることが、とても大切なのではないかと、わたしは強く思います。
そして、そのバランスを家庭で実践することはもちろんですが、家庭以外の場所でも築いていくことができたら、さらに素晴らしいですよね。
たとえば、わたしたちは北極老人の実の子ではありませんでしたが、実の子以上に深い愛情をかけていただきました。そして、その塾という「場」にいさせてもらうだけで、自然と「もっと勉強しよう」「世の中のために何かできることはないだろうか」といった志が、内側から湧き上がってきたのです。
ですから、家庭という小さな枠組みの中だけで考えるのではなく、会社やお店を経営されている方であれば、その職場やお店といった場所でも、このような「安心感」と「方向性」がバランスよく存在する環境を作っていくことができれば、それはとても価値のあることではないでしょうか。
子どもの成長段階と、求められるバランスの変化
特に10代、中学生くらいまでは、まず「安心できる空気」の中で過ごすことが、何よりも大切です。その時期の子どもたちに「将来の方向性」を語っても、まだピンとこないことの方が多いでしょう。
もちろん、早い段階から自分の生き方を考え始める子もいますが、多くの場合、自分の進むべき道を真剣に考え始めるのは、10代後半くらいからではないでしょうか。
じつは、北極老人からよく教わったことですが・・・10代後半くらいになると、まるで前世の記憶のようなものが、ふと意識にのぼってくることがある、とも言われています。
自分の内なる声に耳を澄ませ、人生の方向性を見定める大切な時期なのかもしれませんね。