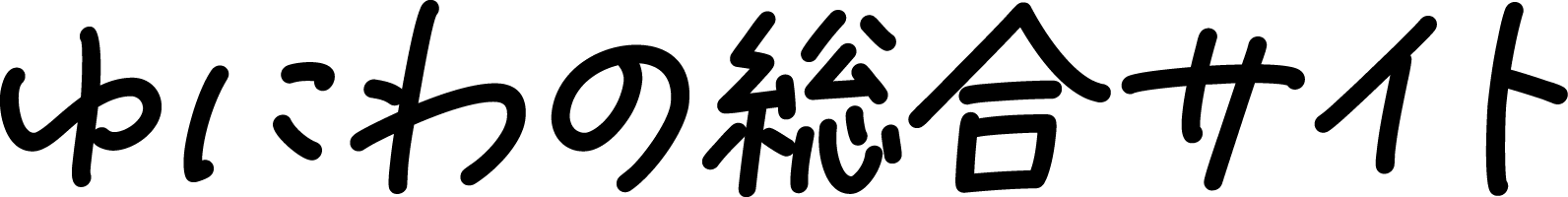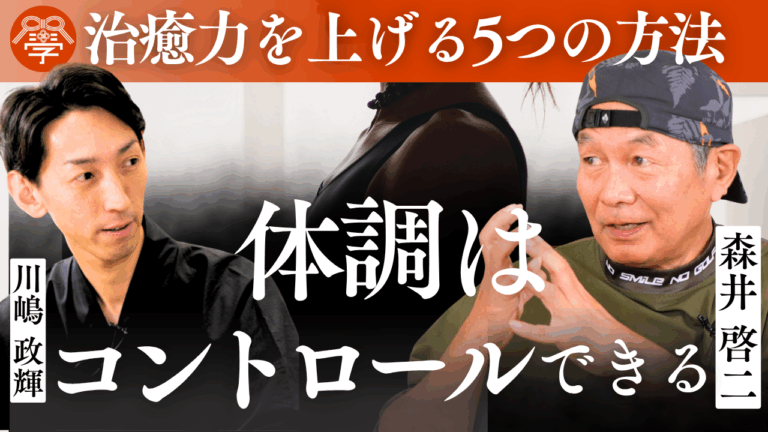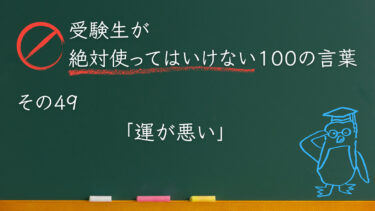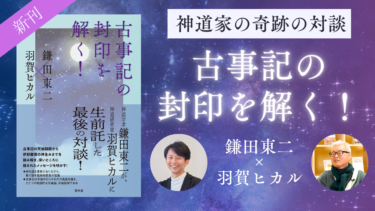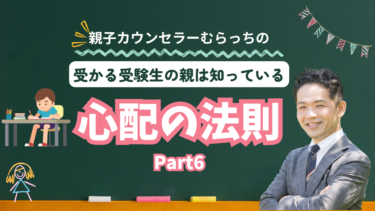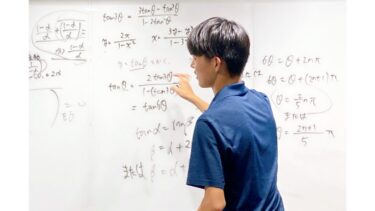前篇は「自然治癒力を高めるには?」
中篇は「身体の奥から元気が湧く健康法」
後篇は「心の土台をつくる〝ヨーガ〟の叡智」
となっています。
(中篇はこちらから
👉【薬からの卒業】自然治癒力を呼び覚ます健康法|森井啓二×川嶋政輝(中篇))

森井:やはり、まず、そうですね、食事はできるだけ自分の細胞にいいような、喜ぶようなものを心がけてはいますよね。
川嶋:それは、身体で感じて反応を見て。
森井:そうですね。ただ、あんまりギチギチにやっちゃう人って、長続きしないので。
楽しくないと、長続きしないと思う。
川嶋:確かに、これも知識で「どういう食事がいい」みたいなものは無数にあるじゃないですか。
「これは避けた方がいい」も含めですけど。
森井:その辺も流されないで、自分自身の細胞にまず聞くのが重要だし、自分の今の現時点での「人生の目的」が明確になってれば、食べるものも決まってくるんですね。
人によって、たとえば「瞑想して極めたい」っていう人と、「できるだけいいタイムで早く走りたい」っていう人だと、食生活も全然違ってくるわけで。
だから、その人生の目的によって、自分の細胞に聞いて、その時の食事を「楽しく」組み立てるというのが非常に重要で。
楽しくないと、絶対長続きしないので。
川嶋:これは、シンプルな話なんですけど、すごく本質的ですよね。
やはり、何を選ぶかとか、そういう手段から入ってしまうけれども、先にその人生の目的があるからこそ、「じゃあ、それに必要な食事は」とかいうのが決まってくる。
結局、目的というのは人それぞれで、最適な食事とか食べ方も、究極的にはいろんなものが必要になってくるということですね。
森井:体質も違うし、消化力も全員違うので、やはり一人ひとり、食べ方も食材も、自分でしっかり選ぶのが一番いいとは思うんですけど。
ただ、現代の食生活は、思いっきり乱れているので。
川嶋:ですよね。普段、森井先生ご自身はどうされているんですか?
森井:**わたしは基本、ほとんど自炊ですね。
川嶋:へえ! そうなんですね。
森井:ただ、そんなにぎっちりやらないで、楽しんで、緩く作ってますね。
川嶋:そうですか。それもシンプルな和食みたいな感じなんですか?
森井:わたしは和食ですね。本当にシンプルに作ってます。
お味噌、醤油、みりん、お酢使って。
あんまり砂糖はいっぱい使わないんですけど。
川嶋:砂糖を避けるのは、どういう理由があってですか?
森井:いや、別に避けているわけではなくて、どっちかっていうとしょっぱいもののが好きなので。
川嶋:身体が欲しなくなったってことなんですね。
森井:そうですね。そんなには。
甘いものでも、たまにはもちろん食べますけど、そんなには使わないですかね。
川嶋:それもね、やはり甘いものもすごく中毒性があるので。
森井:そうですね。人にもよると思うんですね。
だからわたしも、「食べたいな」と思った時にはもちろん食べますし、その辺は制限かけないですけど、でも、だんだん自分の方向性って、毎日ちゃんと自炊していると決まってきますね。
食材選びも、食材を丁寧に、ゆっくり手に持ってると、どうやって調理したらいいか、自分の体と食材が、なんか教えてくれるような気になってくるんですよ。
川嶋:対話するんですね。
森井:そうです、そうです。それで決めていくっていう。
言葉を超えて「全体」を見る
川嶋:森井先生ご自身、獣医師として、言葉の通じ合わない動物たちの声を聞かれると思うんですけど、そこは、やはり感覚的に通じるものがあるんですか?
森井:そうですね。
やはり動物の直感って、人間にも本当に必要で。
よくわたしは、獣医さんとお医者さんと両方に呼ばれて、学会で講演することがあるんですけど、やはり人間のお医者さんって、患者さんの「言葉を聞いて分析する」のが、ものすごくうまいんですよ。
でも、獣医さんは、患者さんの言葉を聞いて分析するっていう能力よりも、目とか、目の動きとか、仕草とか、全体的なエネルギーレベルとか、触った感触。
これは、やはり、すごい得意なんですよ。
川嶋:なるほど。へえ、面白いですね。
森井:だから、それを両方合わせると、より多角的に、総合的に見れるかな、っていうのはありますね。
川嶋:やはり、現代医学でデータや症例ばかり頭に入っていると、もう患者さんを見ずに診断する、みたいなこともあったりしますけど。
森井:でも、今後、医療は今どんどん変わっているので、大半は今後、AIができる部分ってAIになっていくと思うんですね。
もう近いうちに始まっているので。
ただ、その時に、絶対にAIでできないのは、動物で言ったら、体のエネルギーレベルとか、目つきとか、目の動きとかから判断するもの。
それは、AIでは絶対、今の時点ではできないので。
そういったものを組み合わせれば、より深く見ることができるんですね。

川嶋:なるほど。
森井:それを、診察だけではなくて、日常生活にも応用していくっていう。
多角的に、より目に見えるものを超えて見る、っていう習慣がつきやすくなるんですよね。
ヨガの基本「あるがまま」に見る習慣
川嶋:なるほど。
その「目の前のものをよく見る」っていうのは、見てるようで見てなかったりするじゃないですか。
たとえば、同じコップでも「あ、紙コップね」みたいな感じで。今まで人生の中でごまんと見てきた紙コップとイコールと思って見てしまいがちだったり。
そういう「ちゃんと目の前のものを見る」ことも、ヨガと関係しているんですか?
森井:そうですね。
ヨガの場合は、とにかく自分の知識とか偏見とか経験とかを入れずに、まず、「あるがまま見る」んですね。
「あるがまま」なんです。それがすごい重要で。
そうすることによって、そこから内側から引き出してくるものっていうのがあるんですよ、感覚が。
川嶋:あ、自分の中から感覚が出てくる。
森井:そう。
普通の人って、何を見ても、自分の知識と経験と偏見を合わせたフィルターでまず見ちゃう。
だけど、そうすると見る対象が思いっきり限定されちゃうんですね。
川嶋:あ、確かにそうですね。
森井:それを全部外して、ただそのものを、本当に生まれて初めて見るかのように、眺めて、しっかり見て、観察をする。
というのが、ヨガの基本でもありますね。
川嶋:なるほど、それがヨガの基本だと。
でも、それを目の前の食材、今から調理するニンジンや大根や白菜を見た時にも、そういう眼差しで見るんでしょうか?
森井:みんな、なんか普段見てるようで、じつはよく見てなくて。
いや、見てないと思いますね。
ニンジンを見てみると、ヘタの構造が「あ、こんななってるんだ」とか。

玉ねぎの、あの層のなり方とか、ゆりの根の剥いた時の感触とか形とか。

「あ、こうなってるんだ」っていうのが、改めてゆっくり見ると、なんか、生まれて初めて見たかのような感覚になると思うんですけど。
そういった新鮮さっていうのを常に、毎日毎日しっかり見てると、毎日がすごい楽しくなるんですよね。
川嶋:なるほど。
それが頭じゃなくハートの感覚に近づいていくってことですよね。
森井:そうですね。
体より心。生まれ変わっても「持ち越せる」もの
森井:それが結局は心の土台になっていくので。
心の健康になって、体の健康に繋がっていくという感じになりますね。
川嶋:いや、これはすごい大事なお話をいただきました。
森井:だから、体だけ鍛えて…それと同時に心を鍛えるってのもあるし。
でも、心をしっかり鍛えることによって、より体は鍛えやすくなるので。
まずどっちが優先かって言うと、「霊主・心従・体属」で、まず心をしっかり、土台を鍛えるのは、絶対やった方がいい。
心は、生まれ変わっても持ち越せるものが大きいので。
でも、体はどんなに鍛えても、生まれ変わったら持ち越せないんですよ。
川嶋:ですよね。
しかも、どんどん年齢と共にも衰えていくものですし。
森井:そう。
だから最近、ボディビルの方なんかでも、体だけ鍛えるのではなくて、心をちゃんと清らかに正常化しようとか、心を鍛えようっていう人も結構出てきていて。
川嶋:そうなんですね。
確かに、でもそうじゃなかったら、それこそ「ドーピングしたれ!」とか、ステロイド使ったりみたいな、心の弱さに負けるっていう場合もありますから。
森井:そうですね。
「適当に、楽しく」物事を見る
川嶋:いやでも、すごく日常に根差した本質的なお話でした。
この「ちゃんと、あるがまま見る」「ハートで見る」っていうことは、食事でもそうですし、やはり自分の周りの環境とかもそうだなと。
「今のこの会社が」とか「家庭が」とか「関わってる人が」っていうことに対しても、やはりすごく偏見が入ってしまいがちですね。
森井:そうなんですよ。
だから、たとえば職場で悩んでいるとしても、それ自体が自分のフィルターを完全に通していて。
だから、その悩みを他の人に打ち明けると、他の人はフィルターを通さないで客観的に見れるわけですよ。
だから、別に動揺しないし、その相談受けた方は、別に怒るようにもならない。
でも本人からしたら、動揺したり、怒るようになっちゃったりするわけですよ。
それは、自分のフィルターを通して見ているから、そうなっちゃうんですけど。
それを、「しっかり今いる環境で、いろんなその課題をもらっている」っていう感覚でいると、いい意味で、心をしっかりと浄化もできるし、鍛えられることにも繋がっていくんですよね。
川嶋:結局、心が病んでしまうと。
森井:そうですよね。そっからきますもんね。
まず、そこの部分で大らかに。
だから、あんまり真面目すぎるっていうのは良くなくて。
ちょっと適当に、楽しくする方が、絶対に丈夫になると思いますね。
川嶋:なるほど。ありがとうございます。
いや、今日のお話もすごく実践的だったんですけども、次、11月8日(土)にお越しいただく際は、「合掌」のヒミツについてのお話をしていただくということで。

わたしもまだその内容を知らないので、非常に楽しみにしております。
是非ですね、そちらのイベントも、大阪梅田オーバルホールの方で行いますので、ご都合が合いましたら、是非お越しください。
ということで、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
日本をかっこよく! むすび大学でした。