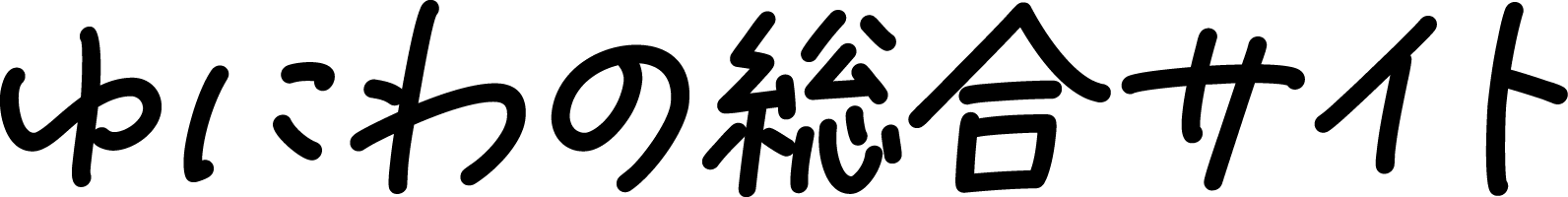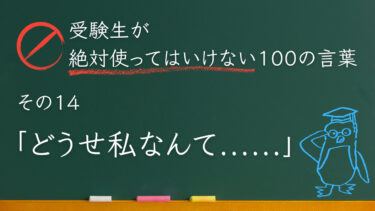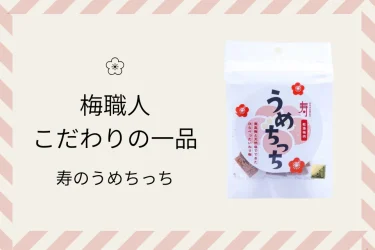伝統音楽と聞くと、なんだか少しむずかしそうで、遠い世界のことのように感じるかもしれません。
でも、じつはわたしたちの文化に深く根付いた、とても美しくて面白い音楽なのです。
ゆにわには、スタッフで結成された「雅楽隊」があります。
2021年から活動をはじめ、各所で演奏する機会もずいぶん増えてきました。
先日の「むすび祭り」でも演奏をお披露目したのですが、お客様からは「はじめて聴くのに、どこか懐かしい」というご感想をたくさんいただきました。
そこで今回は、「これを知って雅楽を聴けば、より楽しくなる!」という基本のキをご紹介します。
この記事を読み終わるころには、きっと雅楽を聴いてみたくなるはずです。
そもそも雅楽って、どんな音楽?
雅楽は「世界最古のオー-ケストラ」と呼ばれています。
その歴史は1300年以上も前にさかのぼり、主に中国大陸や朝鮮半島から伝わった音楽が、日本に古くから存在した歌や舞と融合し、平安時代に現在のスタイルを確立しました。
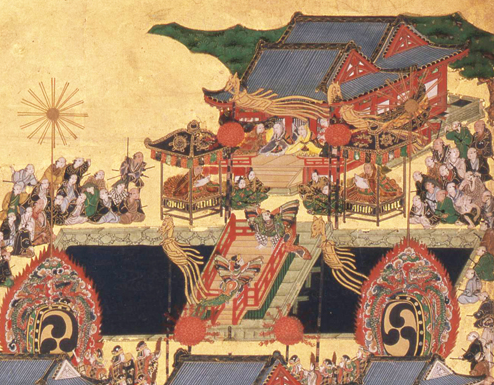
▲『難波名所図屏風』より▲
古来より、宮廷はもちろん、寺社仏閣において「神様に捧げるもの」「神様をお迎えするもの」として演奏されてきた、格調高い音楽です。
「雅(みやび)な楽(うたまい)」という名前の通り、その調べはとても荘厳でゆったりとしており、聴いているとまるで時間が止まったかのような、不思議な感覚に包まれます。
オーケストラ(西洋音楽)とどう違う? 雅楽の魅力
雅楽の面白さは、わたしたちがふだん聴き慣れている西洋のオーケストラと比べてみると、よくわかります。
一番の違いは「時間」の感覚かもしれません。
西洋音楽がメトロノームで刻むような均一なリズムで奏でられるのに対し、雅楽では、寄せては返す波や深く長い呼吸のような、より自然に近いリズムで演奏されます。
「1、2、3、4」という拍子はありますが、等間隔ではなく、拍と拍の間に不規則に生まれる「間」が、雅楽特有の緩急を作り出すのです。
また、雅楽のメロディーは、西洋音楽ではあまり一般的ではない作られ方をしています。
雅楽では、一つのメロディーを複数の楽器が同時に奏でますが、それぞれが微妙に違う装飾音やリズムを持ちます。
つまり、同じメロディーをあえて少しずらして演奏することで、音の響きがより豊かに聞こえてくるのです。
これにより、音がきれいに混ざり合うというよりは、それぞれの楽器の個性が立ちながらも、どこか一体感のある、独特な雰囲気が生まれます。
指揮者がいないのに、なぜ一体感が生まれるの?
そしてもうひとつ、大きな違いがあります。
それは「指揮者がいない」ということです。
西洋のオーケストラでは、指揮者が全体の中心となり、すべての演奏者はその合図に合わせて演奏します。
しかし雅楽では、演奏者一人ひとりが周りの音を聴き、お互いの「呼吸」を感じながら、心をひとつにして音楽を創り上げていくのです。
この「息を合わせる」ということについて、合気道家で整体師でもある三枝誠(さえぐさ まこと)先生が、とても興味深いお話をされていました。
三枝先生によると、そもそも人間は、呼吸をするための専門の筋肉を持っておらず、呼吸が上手ではない生き物なのだそうです。
はるか昔、わたしたちの祖先である魚にはエラがありました。
そのエラを動かしていた筋肉が、進化の過程でどこへ行ったかというと、なんと「表情筋」になった、というのです。
だから、ひととひととが本当に「息が合っている」とき、わたしたちの表情は自然と穏やかで、にこやかになります。
そして、そういうときにこそ、一番呼吸が深くなるのだそうです。
雅楽の演奏者が深い呼吸で心をひとつにしているとき、その音色を聴いているひとたちも、無意識のうちにその呼吸に同調し、心がほどけてやわらかな表情になっていくのでしょう。
このように、雅楽はただ古いだけではなく、ひととひととのつながりを大切にしながら、その関係によって継承されてきたという、日本人らしい温かさが込められた音楽なのです。
どんな楽器で演奏される? ゆにわ雅楽隊のご紹介
雅楽演奏で使われる楽器を、ゆにわの雅楽隊とともにご紹介しましょう。
1.三管(さんかん)~メロディーを奏でる管楽器~
笙(しょう):
見た目も美しい、鳳凰が翼を休めている姿にたとえられる楽器。
「天から差し込む光」を表すと言われ、幻想的な和音を奏でます。


篳篥(ひちりき):
雅楽の主旋律を奏でることが多い縦笛。
小さいながらも、ひとの心の奥に響くような、力強い音色が特徴です。


龍笛(りゅうてき):
その名の通り、天と地の間を舞う龍の鳴き声にたとえられる横笛。
澄んだ音色と軽快な動きで演奏に彩りを加えます。


2.両絃(りょうげん)~リズムを刻む弦楽器~
楽琵琶(がくびわ):
7世紀の末ごろ、他の雅楽器とともに中国から伝来。
各種の琵琶の中では最も大きいと言われ、しゃもじ型の撥(ばち)を使って演奏します。


楽箏(がくそう):
日本の琴(こと)の原型とされる弦楽器です。

3.三鼓(さんこ)~テンポを導く打楽器~
音楽全体のテンポを主導する3種類の打楽器です。



各楽器特有の音も魅力的ですが、これら全てが合わさったときの響きは、なんとも言えないほど心地よいものです。
まるで昔の日本にタイムスリップしたかのよう。
他の音楽では味わえない独特の魅力を感じていただけるでしょう。
雅楽はどこで聴けるの?
「じゃあ、実際に聴いてみたい!」と思ったら、どこへ行けばよいのでしょうか。
神社やお寺
お正月や例大祭、結婚式など、大きな行事の際に演奏されることがあります。
雅楽のルーツに触れるには、最も雰囲気のある場所かもしれません。
コンサートホールや劇場
国立劇場などをはじめ、全国のホールで雅楽の演奏会が定期的に開かれています。
プロの演奏家による、質の高い演奏をじっくりと楽しむことができます。
インターネット
もっと気軽に聴いてみたい、という方には、動画サイトがおすすめです。
「雅楽」や「Gagaku」と検索すれば、たくさんの演奏動画を見つけることができますよ。
ちなみに、
9月20日(土)に、ゆにわ塾主催で開催される「元伊勢籠神社参拝セミナー」でも、ゆにわの雅楽隊が演奏します。
生演奏の迫力をお楽しみいただけますよ。

神社のお話とともに、雅楽の調べにも身をゆだねてみてください。
なつかしさと新鮮さが合わさった、素敵な時間を過ごされることでしょう。
詳細はこちら▽
https://info.hokkyoku-ryu.com/5660/