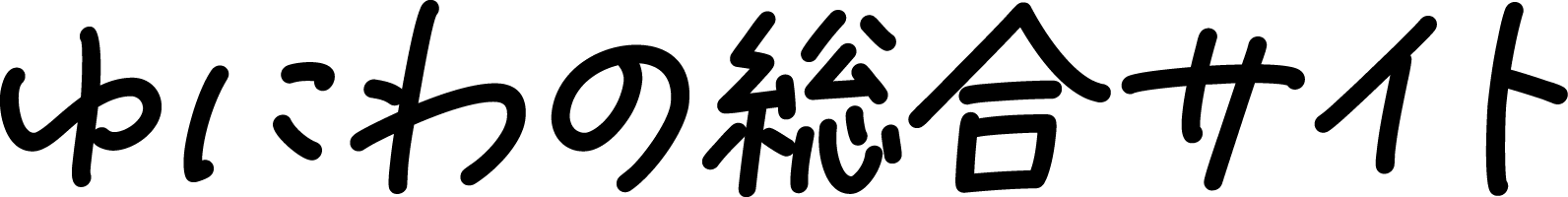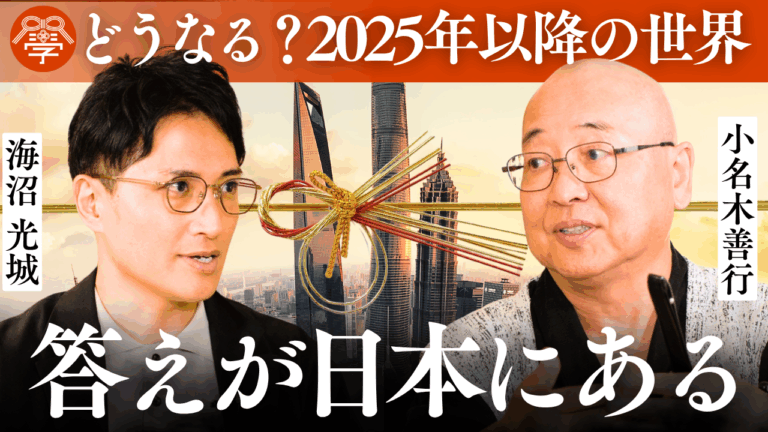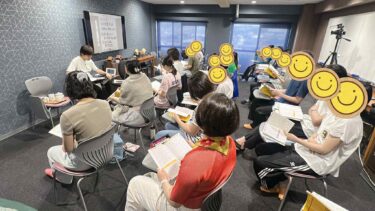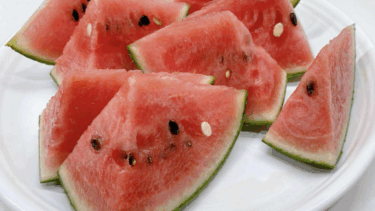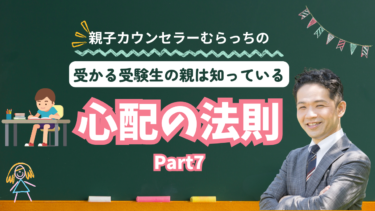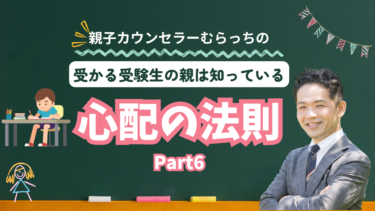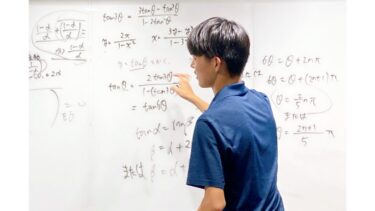前篇は「宗教と社会構造の根深い問題」
中篇は「10万年を超える日本の伝統文化」
後篇は「未来を変えるわたしたちの選択」
となっています。
(前篇はこちらから
👉対談:海沼光城×小名木善行|日本の未来は〝むすび〟の精神にあり【前篇】)
<10万年を超える日本の伝統文化>
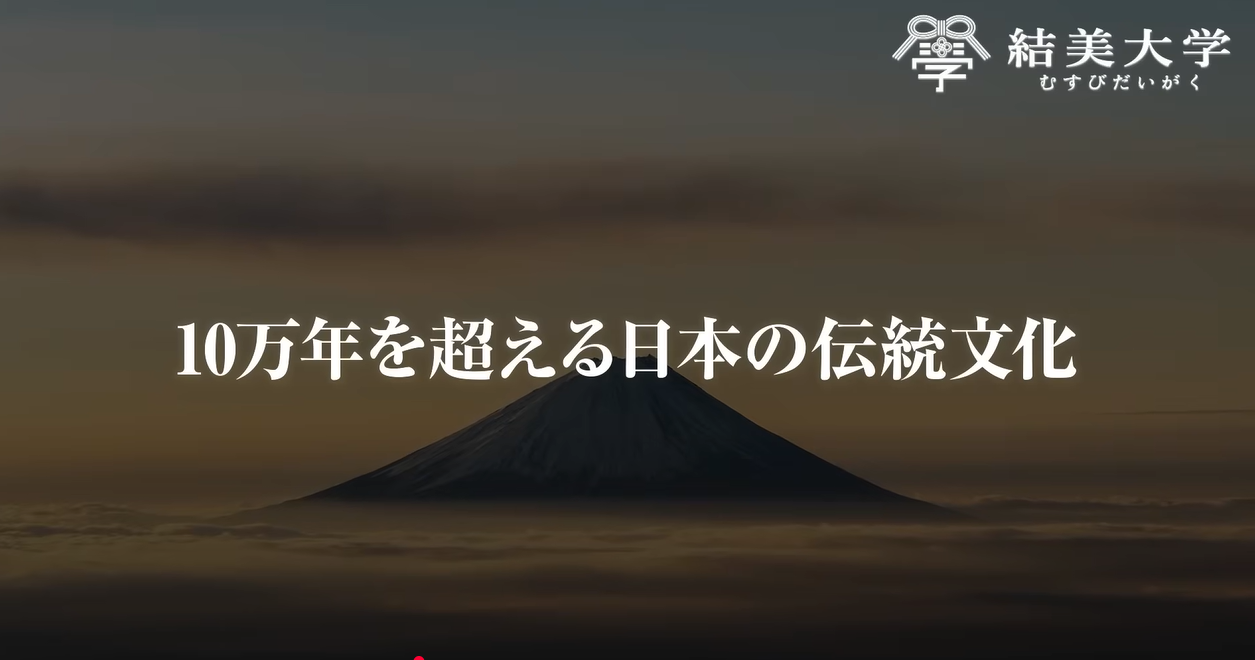
小名木:まず非常に大事なポイントとして、未来というものは突然現れるものではない、ということです。
つねに積み重ねによって、その結果が未来になっていきます。
ですから、今の延長線上に未来はあります。
しかし同時に、未来にはいろいろな選択肢があるわけです。
どの未来を選択するかは、まさにいまこの瞬間によって決まっていきます。
いま、わたしたちがどの方向に向かおうとするかによって、人類社会の未来は全く違う方向へ進む可能性があるのです。
マックス・ヴェーバー式に言えば、人類社会は「支配」というものがなければ成り立ちません。
それがAIによって支配されるのか、あるいはAIを支配できる一部の特権階級によって世界中の人々が支配されるのか。

これをディストピアや奴隷社会だと言う人もいますが、そうした未来へ向かう選択も、もちろんいまこの瞬間に存在します。
そういうものを好む人々は、そういう世界へ行くことになるでしょう。
しかし、わたしたちが望んでいるのはそうではありません。
たとえば、縄文時代の人々が山や海を眺めながら、自然とともにあるがままに祈りを捧げていた精神。

その精神構造が、ときを超えて神社の祭りや農耕儀礼、日々の言葉遣いや書画といった形で、今に築かれてきています。
これが大体どのくらい前からあるかというと、縄文時代は約1万7000年前に始まりますが、じつは日本の場合は旧石器時代、3万8000年前からその文明の系譜があります。
神話の時代になると、その倍くらい古くなります。
これにはわたしもびっくりしたのですが、阿蘇に健磐龍命(たけいわたつのみこと)という神様がいます。
この神様は、伊奘諾(いざなぎ)や伊奘冉(いざなみ)、天照大御神(あまてらすおおみかみ)などと比べると、ずっと後の時代の比較的新しい神様です。
この神様が何をしたかというと、九州の阿蘇山は、外輪山に囲まれた内側にカルデラがあります。
じつは、大昔このカルデラの内側は湖だったのです。
健磐龍命は、「こんなところに湖があっても何の役にも立たない。この水を抜けば畑が作れて、みんなが楽に暮らせるようになるじゃないか」と考え、阿蘇の山に一人で登り、外輪山の一部をドーンと蹴り飛ばしました。
それによって湖の水が一気に流れ出し、現在の阿蘇のカルデラ内に人々が住めるようになった、ということを成し遂げた神様として有名です。

最近の研究で、阿蘇山の内側が本当に湖だった時代があったこと、そしてその水が抜けた時期も明らかになりました。
抜けた場所は地図を見れば一発で分かりますが、その時期が特定されたのです。
つまり、健磐龍命が山を蹴り飛ばしたのはいつか、ということです。
海沼:何年前でしょうか。さっきの話からすると、6万年くらい前ですか?
小名木:良いところを突いていますね。答えを申し上げます。
7万3000年前です。
7万3000年前の出来事を、わたしたちの祖先は神話という形でちゃんと記憶しているのです。
海沼:すごいですね。それが実際にあったということですか。
小名木:はい。その健磐龍命でさえ、7万3000年前の比較的新しい神様なのです。
では、大元の神様はどのくらい前になるのかというと、おそらく15万年くらい前ではないか、という話になります。
ですから、よく「日本の歴史にとって3000年なんて、ほんの瞬き一回分くらいの期間でしかない」といわれますが、まさしくその通りで、日本は本当に古くて長い歴史を持っています。
その中で、海面が今より140m低かった時代もあれば、逆に22mも高くなった時代もありました。
22mというと7階建てのビルに相当しますから、その7階までが全て海の底だったわけです。
そのようなさまざまな時代を経験し、途中に火山の噴火や異常気象もあり、台風は毎年やってくるという中で、わたしたちの祖先はなんとか頑張って生き抜き、自分たちが生きた時代よりももっと良い時代を子どもたちに残そうと努力を重ねてきました。
この10万年を超える人々の振る舞いの積み重ねが、今の日本を作っているのです。
日本は一朝一夕にできたわけではありません。
そうした中で育まれた精神の流れの中で、非常に大切にされているものが「共同協心(きょうどうきょうしん)」の文化です。
共に心と心を触れ合わせ、共に感動し、共に味わう。
共に心が震える、という意味です。
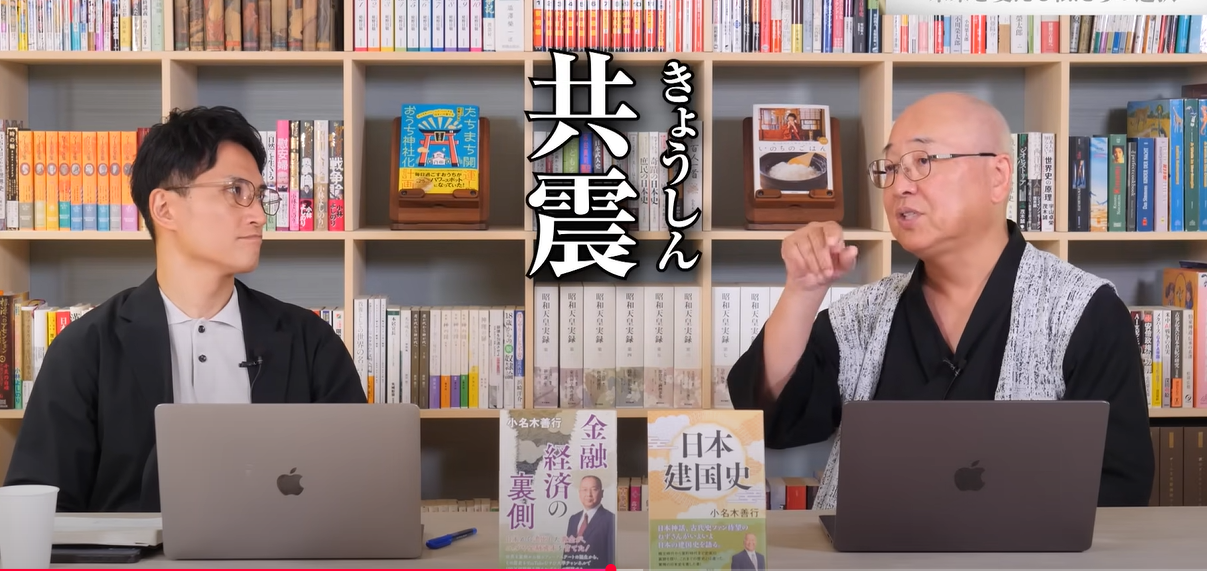
たとえば食事をする場合でも、一人でこっそり美味しい牛肉を買ってきて食べるのではなく、みんなで共に味わうことで喜びを感じる、そういった文化を発達させてきました。
その中での日本の構造で非常に面白いのは、マックス・ヴェーバーの考え方にも通じるところがありますが、一定の支配層はいる、ということです。
野球でも監督やコーチが必要なように、社会の構造そのものを監督する役割の人は必要です。
しかし、その中でプレイをするのは選手です。
「監督は偉そうなことを言っているけれど、実際にバットを持たせたって全然打てないじゃないか。試合をやるのは俺たちなんだ」と、現場の第一線の人たちがまさに主役となって生きていくことができる社会。
これが日本型の共生社会として形成されてきました。
このことが、日本の文化の柱になっているのだと思います。
おそらく、イーロン・マスク氏が言っている「日本に学べ」という言葉が指し示す日本とは、江戸時代であったり、奈良・平安の昔であったり、あるいは縄文の昔にまで遡っていくような話になるのだろうと思います。
(後篇につづく
👉対談:海沼光城×小名木善行|日本の未来は〝むすび〟の精神にあり【後篇】)