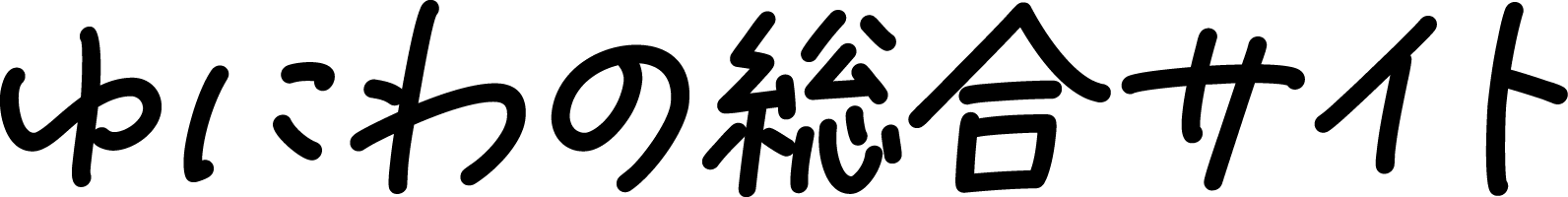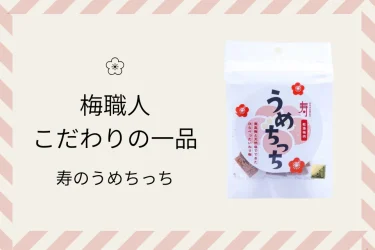前回のコラム
「藍(あい)染めの力──美しさと機能を備えた、日本の知恵」
という記事では、
紫外線予防にもなるといった藍染の特徴や、
正藍染めの衣類を手作りされている
「あいわゆう」さんの活動をご紹介をさせていただきました。
今回は、正藍染めの世界の中でも、
さらに「色」について深掘りしてご紹介したいと思います。

日本人の美意識を伝える「藍四十八色」
藍染めといっても、色は様々。
染める回数を重ねるごとに、藍は濃く、深く染まっていきます。
そのため、藍色には一番薄い「藍白(あいじろ)」から、一番濃い「留紺(とめこん)」まで、実に48種類もの色合いがあると言われています。
それらは、敬意を込めて「藍四十八色(あいしじゅうはっしょく)」と呼ばれています。
この「藍四十八色」という言葉は、単に色数が多いことを示すだけでなく、一つひとつの色に込められた名前や歴史、文化的な意味合いを伝える表現でもあります。

戦国武将が愛した「勝色(かちいろ)」とは
そんな48の藍色の中に、「勝色/ 褐色(かちいろ)」と呼ばれる色があります。
これは、いわゆる紺色よりもさらに濃く、黒と見まごうほどの暗い藍色のこと。
藍を濃く染め上げるために布を叩く「搗(か)つ」という作業の音が「勝つ」に通じることから、武士たちに「勝ち」を連想させる縁起のよい色として、特に好まれました。
実際に、勝色に染められた軍旗(ぐんき)を掲げて戦に勝利したことから、縁起物として「勝染(かちぞめ)」と呼ぶようになった、とも言われています。
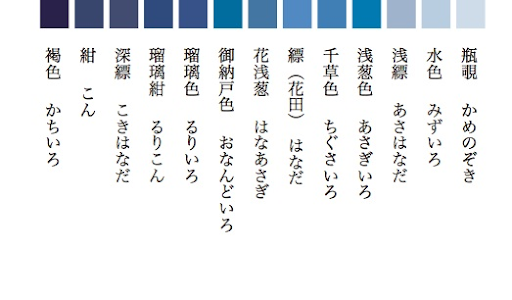
※芦屋市立美術博物館より
歳月をかけて育て上げる、深く濃い藍
今週末に開催される、あいわゆうさんの展示販売会では、この「勝色」の作品を実際にご覧になることができます。
ゆにわ塾講師のこがみのりさんが、参拝セミナーで太鼓を叩くときに着用している衣装です。 あいわゆうさんに、特別に誂(あつら)えてもらったのだそうです。


あいわゆうさんは、この色を出すために大変な手間と時間をかけられています。
「染め・洗い・天日干しの工程を30回以上繰り返し、約2年の歳月をかけて染め上げた勝色(褐色)です。
老年の藍甕(あいがめ)が醸すやわらかな空色から染め始め、やがて若い藍甕へとバトンを渡しながら、黒と見紛うほどに深く濃い藍色へと育て上げました」
このように語る、あいわゆうさんの言葉からも、その一色に込められた想いが伝わってきます。
また、こがみのりさんも、
「この勝色の衣装を着て太鼓を演奏したらすごく心地よくて、音の響きが変わりました。
お客様からもすごく好評でした」
とのこと。
手間と時間をかけて生み出された色、そして、長い歴史をわたって多くの人から愛される色には、秘められたパワーがあるのかもしれません。
ぜひ会場にて、「黒と見紛うほどに深く濃い藍色」をご覧ください。
きっと藍染めの奥深い色の美しさに魅了されることでしょう。
+++++++
※こちらのイベントは終了しました。
「正藍染」の衣類についてもっと詳しく聞きたい!
そんな方には、「あいわゆう」さんのトークショーへどうぞ。
7月6日(日)(大阪・楠葉)
「あいわゆう」正藍染め作品の展示販売会とトークショー

正藍染めの魅力を語るトークショーは、参加費は無料です。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお越しください。
今年の展示会とトークショーの詳細はこちら!
https://uniwamart.com/blogs/notice/aiwayuu
+++++++++++++++++++++++++
「あいわゆう」さんの作品は、
「ゆにわマートオンラインショップ」にて販売しています。