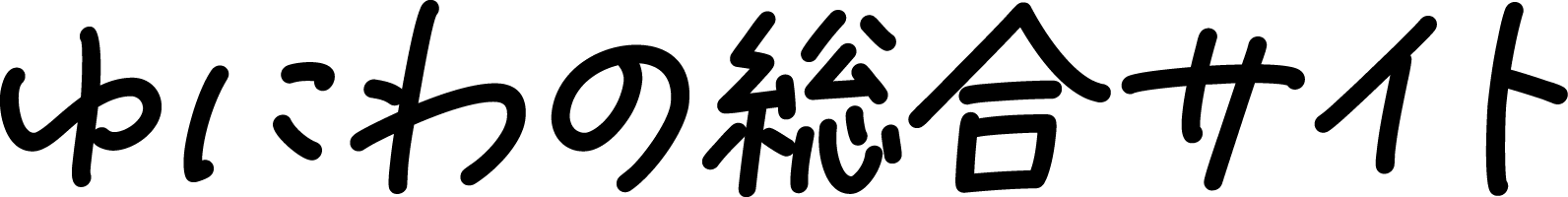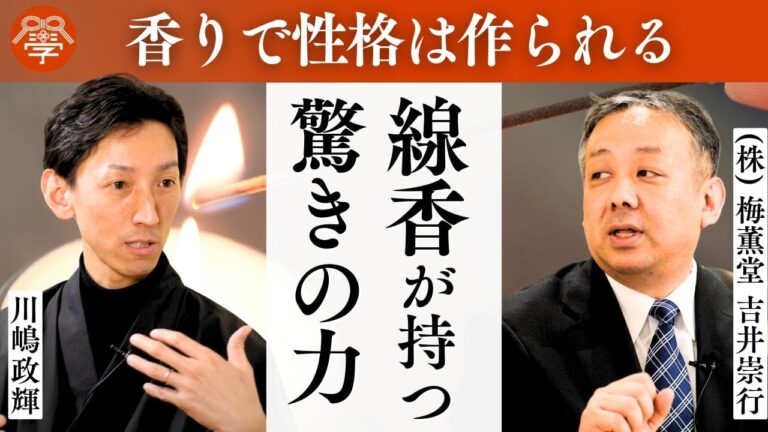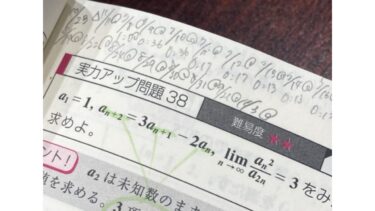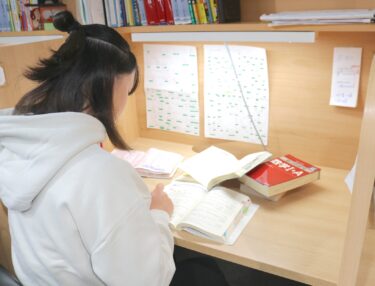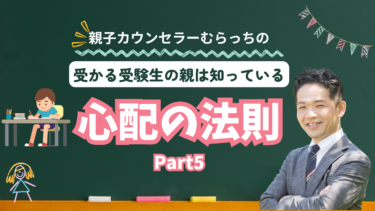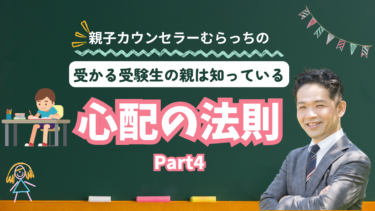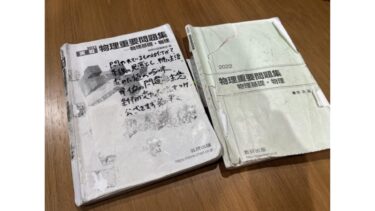この記事は3部構成の【後編】です。【前編】では香りの歴史と国内外での捉え方、【中編】では香りの神秘的な力と科学的な側面について、創業175年の老舗「梅薫堂」の吉井崇行さんにお話を伺いました。最終章となる後編では、私たちの本能と香りの深い関係、そして毎日の暮らしを豊かにする具体的な香りの活用法やおもてなしのヒントを探ります。
香りと本能:無意識下の深い結びつき
「女性は男性を香りで選んでいる」といった俗説を耳にすることがあります。たとえば、年ごろになった娘さんが「お父さん臭い」と言いだすのは、父親とは異なる遺伝子を残そうとする、女性の生物としての本能がそうさせている、という話もあります。
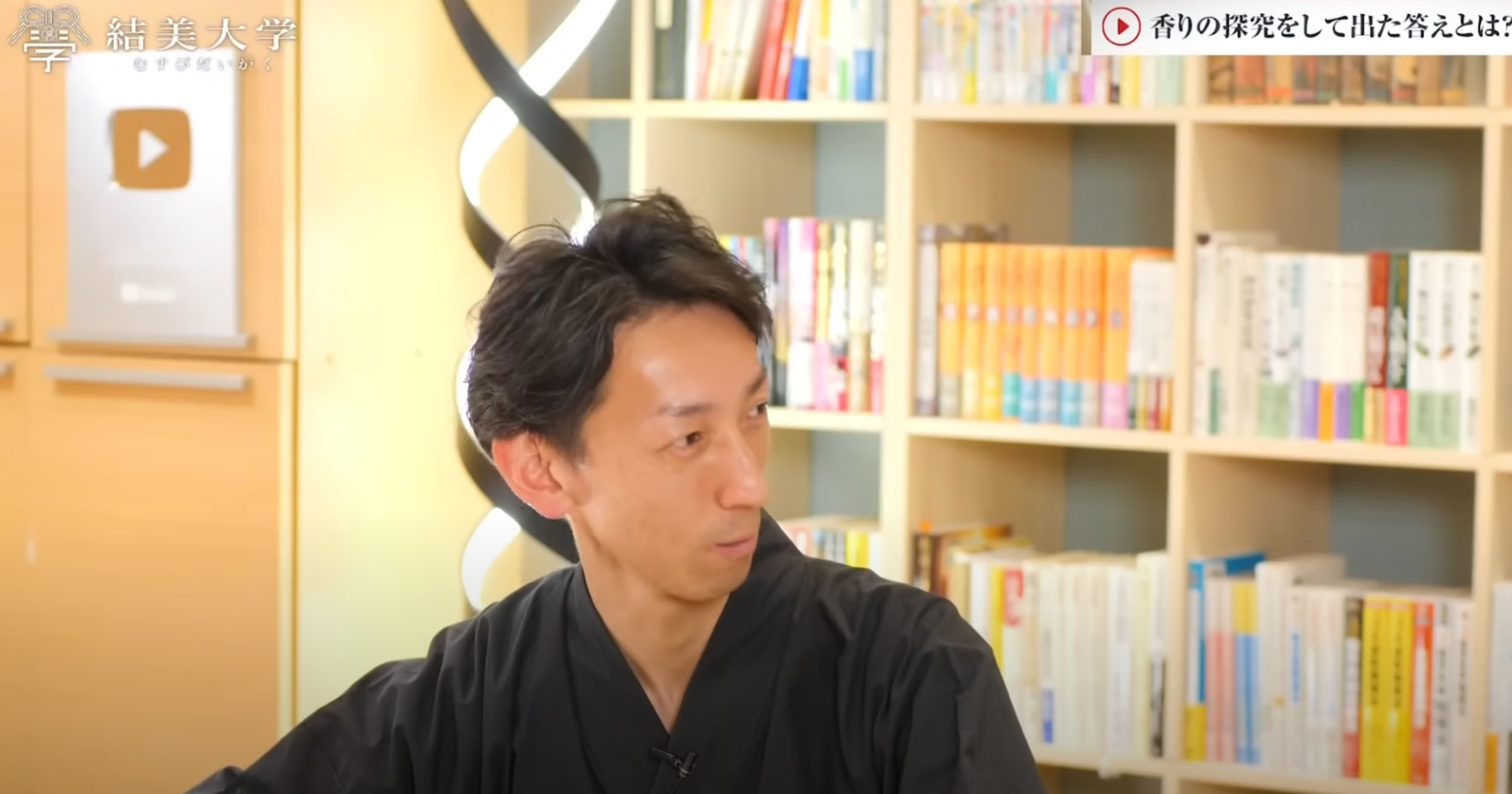
ひとが根源的に持っている本能のような部分と、香りはきわめて密接に結びついているように感じられますが、その点はいかがでしょうか。
吉井さんも、「それはあると思います」と同意します。よい香りの感じかたには個人差がありますが、精神的な部分ときわめて強く繋がっている気がする、とのことです。
現代社会には、化学的に作られた香料があふれています。食品、化粧品、ルームフレグランスなど、さまざまなものに人工的な香りがつけられていますが、わたしはそれが苦手で、頭が痛くなる香りもあります。
吉井さんご自身も、香りの業界にいるため、からだの反応にはある程度慣れているかと思いきや、ある種の香りに対してアレルギー反応が出てしまった経験があるそうです。お線香ではそのような経験はないそうですが、「こういうことが実際にあるのだ」と実感し、「使ってくださる方々が安心して健康に過ごしていただけるものをていきょうしていかなければならない」という意識を、いっそう強く持つようになったと語ります。
香りが意識にあたえる影響が大きいからこそ、普段どのようなものを選ぶかはきわめて重要だと、わたしも思います。
日常を豊かにする香りの活用法
わたしたちが梅薫堂さんのお線香を愛用している理由の一つに、その「清める力」があります。
スタッフもたくさんいますが、ひとはそれぞれ、良くも悪くも考えかたの癖や価値観を持っています。それが、不思議とそのひとの部屋の香りや、そのひと自身が醸しだす香りとリンクしているように感じることがあります。とくに女性は、そういった感覚に敏感です。
たとえば、自分のことばかり考えている男性や、よこしまなことばかり考えている男性、自意識が過剰なひとに対して、女性は「なんだか臭い」と感じることがあるようです。エゴや自我が強い状態が、何らかの「臭い」として感じられるのかもしれません。そして、そう感じられるひとの部屋も、同じような匂いがすることが多いのです。
そう考えると、部屋の香りがいかに大切かがわかります。しかし、自分の香りというのは、自分ではなかなか認識できません。それが自然な状態だからです。
だからこそ、生活のなかに「香り」を取り入れて、一度リセットすることが重要だと考えています。自分自身の香りもそうですが、「いま、自分はどんな香りに包まれた空間にいるのか」を意識的に認識する習慣を大切にしています。そのために、お線香で空間を清めるのです。
空間には、そこにいたひとが考えていたことや思っていたことが、雰囲気として残るように感じます。わたしたちはそれを「残存思念」や「残存感情」と呼んだりしますが、目に見えない「気」のようなものが空間に残るのです。
だから、部屋にはいったときに「なんだか誰かいたのかな?」と感じるような気配も、香りとして残っている可能性があります。それをいったんクリアにしないと、無意識のうちに何らかのネガティブな影響を受けてしまうかもしれない、という認識を持っています。
梅薫堂さんのお線香は、そういった空間の浄化に、まさにうってつけなのです。
実際に、空間の清めといった用途でお線香を使われている方はいらっしゃるのでしょうか。
吉井さんによると、お線香にはそもそも場を清めるという文化的背景がありますが、とくにわたしたちが長年お世話になっている「備長炭麗(びんちょうたんれい)」シリーズは、「匂いを消して(消臭)、場を清める(清浄)」というコンセプトで作られています。

このお線香は、焚いていると嫌な匂いがどんどん消えていくのが特徴です。よくあるルームフレグランスのように、嫌な匂いの上に別の香りを乗せてマスキング(覆い隠す)するのではなく、嫌な香り自体を消していく作用があるとのこと。
お線香にすることで、その効果が煙(煙はすくないですが)に乗って空間全体に広がっていきます。スプレータイプだと効果は局所的になりがちですが、お線香は広く空間全体に行き渡る特性を持っています。そうして、空間が清められていくのですね。
おもてなしとしての香り、心を繋ぐひととき
わたしたちも、イベントや「むすび大学」のリアルセミナーなどを開催する際には、参加される方がもっとも集中してよい精神状態で過ごせるように、事前に会場の掃除を徹底します。外部の会場を借りる場合でも、何十人もで掃除をします。
その際、会場の規定で使えないこともありますが、許可されている場所では、お線香を焚いて空間を清めます。セミナー会場のようにひとが多く集まる場所は、良くも悪くも、以前に利用した方々の「気」が残ってしまいがちです。
「気」は水のようなもので、ずっと滞っていると淀んでしまいます。昔のひとはそれを「邪気」と呼んだのかもしれません。その淀みを流し、清めるという意味で、お線香はきわめて役立ちます。
わたしも師匠が使っているのをみるまでは、「お線香って仏壇に供えるものでしょ?」という認識しかありませんでした。しかし、最近では若い方でもお線香を使うひとが増えているそうですね。
吉井さんのもとにも、若い世代から「お香感覚で使っています」という声や、お香に関する問い合わせが多く寄せられているそうです。「文化を次の世代の方々が支えてくださっている」と感じる瞬間が多いとのこと。インテリアの一部として、癒やしや清めをもとめて、若いひとたちがお線香を取り入れているイメージがありますね。
とくにコロナ禍では、在宅ワークが増え、家で過ごす時間が長くなったため、リフレッシュのためにお線香を使うひとが増えたという話も聞かれました。北米などでも、在宅ワークをするひとたちにとって、お香の文化が効果的であると認識され、流行したそうです。
家の中で手軽に場を清めることができるのは、大きな魅力です。外から不要なもの(邪気やマイナスのエネルギーなど)を持ち帰ってしまったと感じたときに、お線香を一本焚くだけでも、空気が変わるのを感じます。
昔は多くの家に仏間があり、毎日朝晩お線香をあげる習慣がありました。それによって、家のなかによい気の流れができていたのかもしれません。いま、そうした仏間のある家が減っているという声も聞かれますが、この習慣こそが、かつての日本の発展を支えた一つの要因だった可能性もあります。
師匠からは、お線香を焚くときには、どういう意識で火をつけるかがすごく大事だ、と教わりました。供養のため、リフレッシュのため、邪気を払うため、それぞれの目的に応じた意識づけが大切だと。
香りのことを「芳香(ほうこう)」と言いますが、これはまさに、玉(魂)の方向、つまり「意識の方向づけ」をしてくれるのが香りの力なのだと、わたしは解釈しています。
家にいる時間が多い現代、あるいは誰かといっしょに過ごすときに、きもちを一つにしたり、自分ではうまく扱えない無意識や深い部分の意識をよい方向へ導いたりするうえで、香りは大きな助けとなるのではないでしょうか。
日常での使い方と楽しみ方
吉井さんご自身は、日常でどのように香りを活用されているのでしょうか。
朝起きたときにお線香を焚いて一日を始めると、とても清々しく過ごせるそうです。また、家族が帰ってくる夕方に焚くと、落ち着きのある「団欒の間(だんらんのま)」が作られるのを、肌で感じると言います。

お線香は、もともと「お香」のかたちを変えたものです。ですから、「お線香=仏事用」と限定せず、ぜひ「お香」として、癒やしの空間づくりのために活用してほしい、と吉井さんは願っています。
また、お線香は「立てて焚くか」「寝かせて焚くか」で、燃焼時間が変わるというおもしろい情報も教えていただきました。立てて焚く方がはやく燃え尽き、寝かせて焚くとゆっくり燃えるそうです。どちらがよいかは好みですが、わたしは寝かせる派です。ゆっくり香りを楽しみ、場を浄化していくのに向いている気がしますし、立てると根元が燃え残ってしまうのがもったいないと感じるからです。
お線香の燃焼時間について尋ねられることも多いそうで、その際は「立てたら何分、寝かせたら何分」と説明されるそうです。
最近増えているのが、「お線香がすぐ消えてしまう」という相談です。原因を聞くと、陶器のお皿などのうえに直接お線香をおいてしまっているケースがあるとのこと。お線香は、おかれた場所に温度差があったり、燃焼を妨げる障害物があったりすると、燃焼剤がはいっていない場合は消えてしまうのです。
使い方を知らないと、「うまく燃えないけれど大丈夫ですか?」という疑問に繋がってしまいます。その際は、正しい使い方や、専用の香炉・香立てといった道具があることを説明されるそうです。昔はあたりまえだった知識も、知らない方が増えているのですね。
わたしたちは、おもてなしとしてもお線香をよく使います。たとえば、誰かが1時間後に来られるとわかっている場合、ちょうど到着される時間にあわせて、「今日はこの香りでお迎えしよう」と、お線香を焚くことがあります。気づかれないくらいのほのかな香りかもしれませんが、そうした心遣いは、ひとの無意識の深い部分に働きかけ、安心感を生み、おたがいの信頼関係を築く助けになるのではないかと考えています。
おわりに:香りの魅力を未来へ繋ぐ
今回は、創業175年の老舗、梅薫堂の吉井崇行さんをお迎えし、香りの秘密について深く語り合いました。わたしたちもユーザーとして、その魅力を日々実感しています。
本日ご紹介した梅薫堂さんのお線香に興味をもたれた方は、ぜひこちらのリンクからご覧ください。自信をもっておすすめします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。むすび大学でした。