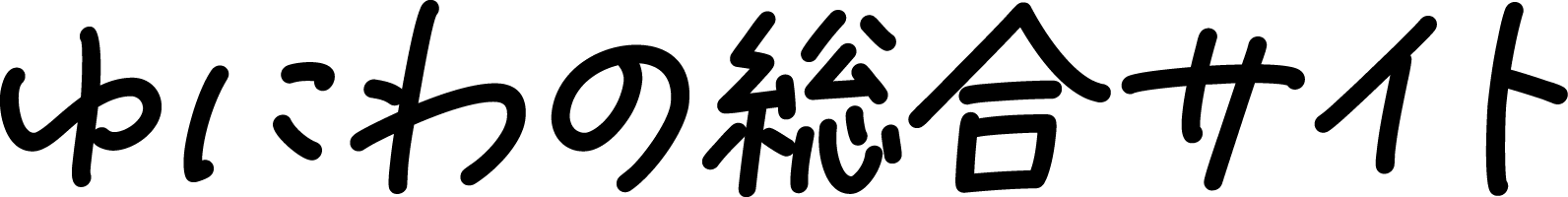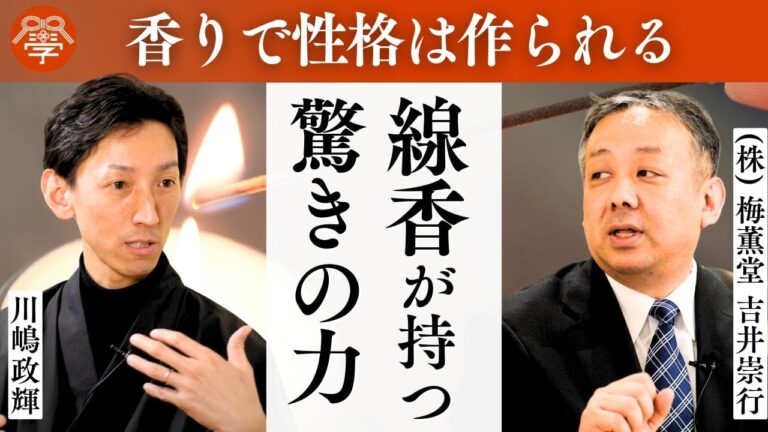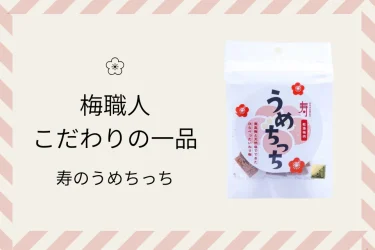この記事は3部構成の【中編】です。【前編】では、現代における香りの重要性、日本と海外での香りの捉え方の違い、そしてお線香の産地・淡路島の歴史に触れました。この中編では、創業175年の老舗「梅薫堂」の吉井崇行さんのお話をもとに、さらに香りの奥深い世界へ。日本書紀に残る香木の伝説から、場を清め心を癒やす香りの神秘的な力、そして科学的なアプローチまでを探ります。
香りの島のルーツ:日本書紀の伝承

さらに歴史を遡ると、じつは『日本書紀』にも、淡路島とお線香に関わるような伝説が記されているのです。淡路島が「香りの故郷」と言われる一つの要因として、この国の正式な書物である『日本書紀』に、香りの記述が登場します。
それは推古天皇3年(西暦595年)の夏4月のこと。「沈水(じんすい)、淡路島に漂い着けり」という記述から始まるお話です。島民が浜辺に流れ着いた大きな流木(香木)を火にくべてみたところ、すばらしい香りがしたため、「これは貴重な木にちがいない」と朝廷に献上した、という心温まるエピソードが記されています。
一説には、この香木が献上された際、当時の政治を司っていた聖徳太子が「これは沈香(じんこう)である」と言って、その価値を知っていたとも伝えられています。すごい話ですよね。
そして、この伝承をいまに伝える神社が、淡路島には存在します。それが「枯木神社」です。
不思議なことに、淡路島ではこの伝承の後、すぐに香りの生産が始まったわけではありません。しかし、江戸時代になって再び「香りの里」となるのですから、何か特別な縁があったのかもしれませんね。
吉井さんによると、梅薫堂のある地域は、合併前は「一宮町(いちのみやちょう)」と呼ばれ、お線香の町として栄え、そこから島全体にお線香づくりが広がっていった中核的な地域だったそうです。そして、その一宮町に、香木の伝承を持つ枯野神社があるというのも、また興味深い偶然です。
香りの神秘的な力:場を清め、心を癒やす
普段、意識的に使わなければ、香りは、なんとなく鼻にはいってきても、すぐに慣れてしまうものです。しかし、じつはひとの意識やありかたに、香りは深く影響をあたえているとわたしは思います。
吉井さんは、お線香を通じて「場を清める力」を強く感じると言います。お線香を焚くこと、あるいは仏様に捧げることで、空間の空気が明らかに変わるのを感じるそうです。供養の場であれば清めとなり、また、空間が清められることで、癒やしの空間が生まれることにも繋がっていくのかもしれません。
お線香の香りには、原料によってさまざまなタイプがあります。たとえば、香木系では白檀(びゃくだん)や沈香(じんこう)。それ以外にも、花の香りや植物の香り、そしてシナモンなど食品や薬にも使われるような生薬を用いた香りもあります。昔ながらのお線香には、杉の葉を粉にして水を加えて固めた、素朴な杉の葉の香りも存在します。
梅薫堂さんのお線香は、ナチュラルなものが多く、香りは比較的よわい傾向にあるそうです。化学的な香料を使えば香りは強くなりますが、自然な香りは穏やかでありながら、「実際に焚いていると心が安らぐ」という声が多く寄せられるとのこと。やはり、自然のものが持つ力というのは大きいのでしょうね。
わたしも師匠に、キャラ(伽羅:最高級の沈香)というきわめて質の高いお香の香りを体験させてもらったことがありますが、そのときは意識がどこかへ飛んでいきそうになるような、ある意味、理性が吹き飛ぶような感覚をおぼえました。
さまざまな宗教儀式で必ずと言っていいほど香りが使われるのは、日本に限りません。仏教で言えば、悟りを開くため、心のノイズをなくし、執着のない清らかな状態に近づくために香りが用いられた側面もあるでしょう。
吉井さんは、まこものお線香を試作していたときの体験を話してくれました。生産現場では、粘着剤の話や素材のおもしろさについて、職人さんたちが熱心に語ってくれるそうです。そして、できあがったお線香を実際に焚いて燃焼実験をするなかで、「このすごくよい雰囲気のパワーは何だ!?」と感じることがあったと言います。
そのパワーを検証する方法はないかと考え、化学的な香料(おそらく芳香剤のようなもの)を近くに置いた空間にそのお線香を持っていくと、不快な匂いがすっと消えて清々しくなったそうです。「実体験として『すごいな』と感じた」と語ってくださいました。

いま、「霊的な話」という言葉が出ましたが、じつはマコモ(真菰)は、古くから神社のしめ縄に使われたり、『古事記』の神話で、大国主命(おおくにぬしのみこと)が傷ついたウサギを癒やすためにマコモで編んだ筵(むしろ)の上に寝かせたりと、日本の古い伝承に深く関わっています。単なるおとぎ話ではなく、そこには最新科学でも解き明かせないような秘密が眠っているのかもしれないと感じさせられますね。
香りと科学:探求の途上にある嗅覚の世界
吉井さんは、もともと理系の研究を志向されていたそうです。香りの研究をしようと大学を目指していた矢先、高校3年生のときに阪神・淡路大震災を経験しました。その経験から、大学では情報処理や人工知能といった、当初とは異なる分野を学ばれたそうです。
しかし、香りへの関心はつねに持ちつづけており、「どういう香りがよいのか」という探求心は持ちつづけていました。香りの領域は、数値化するのがきわめて難しい分野だと吉井さんは言います。多くの要素が複合的に絡み合っているからです。
デジタル技術を学んだ経験から、視覚や聴覚、触覚が数字に変換されていく様子を見てきた一方で、嗅覚は化学反応によって情報が伝達される側面が強く、数値化や再現が難しい領域でした。
現在も、人工知能を使って嗅覚を再現しようという研究は進められていますが、香りの専門家が情報処理技術や人工知能の知識も踏まえて語ることで、またちがう見方が生まれるのではないか、と。まだまだ探求の余地が大きい分野だと考えられているようです。
香りの再現や、香りを嗅ぎ分けるAIやロボットの開発は、まさにいま、研究が進められている最先端のテーマなのですね。
そして、香りというのは、同じ香りを嗅いでも、ひとによって感じかたがちがうのではないか、とも吉井さんは指摘します。
「体調や、住んでいる場所、背景知識によっても感じかたは変わるかもしれません。同じ場所にいる日本人と外国人でも、感じかたがちがう可能性すらあります。好き嫌いがはっきりと分かれるのも、香りの特徴ですね。」
中編では、香りの歴史的なルーツから、場を清め心を癒やす神秘的な側面、そして科学的な探求の現状までを掘り下げました。後編では、香りと私たちの本能との深い結びつきや、日常生活で香りをもっと楽しむための具体的な活用法、さらにはおもてなしとしての香りの使い方について、吉井さんのお話を伺っていきます。